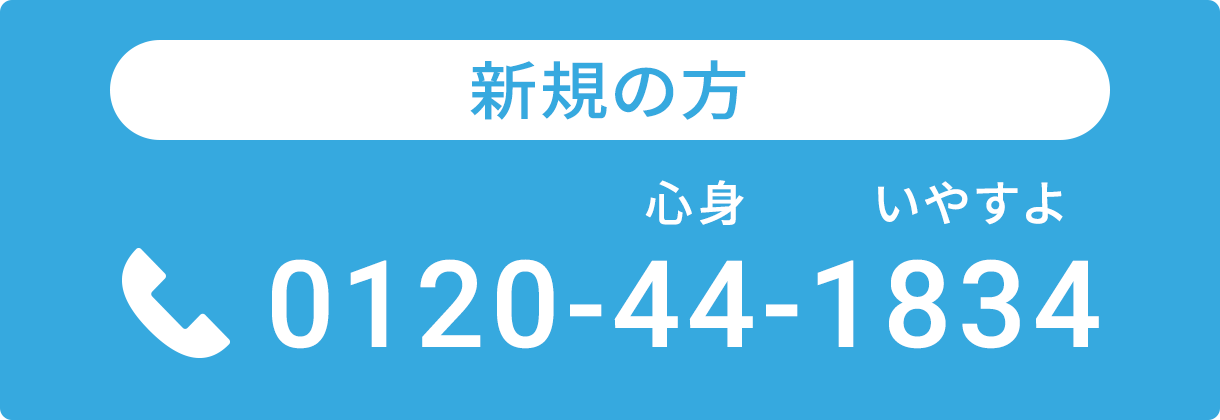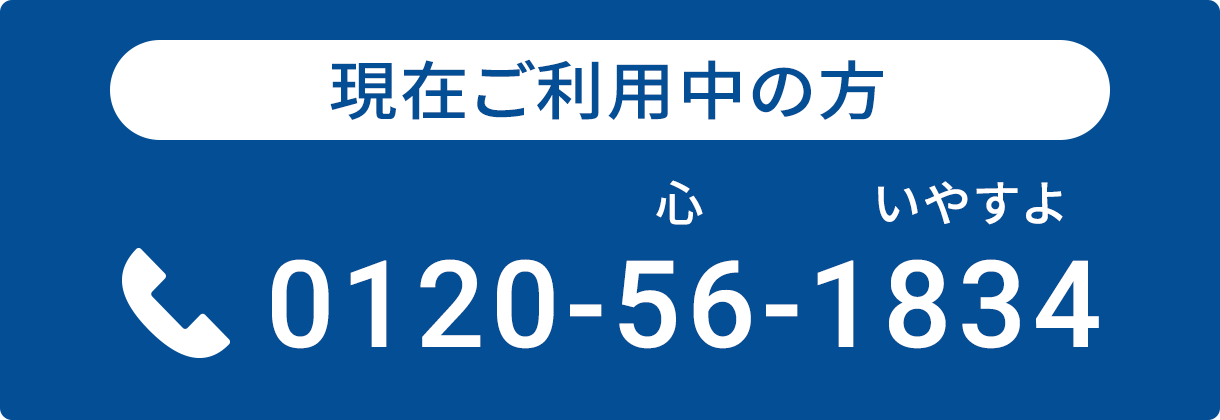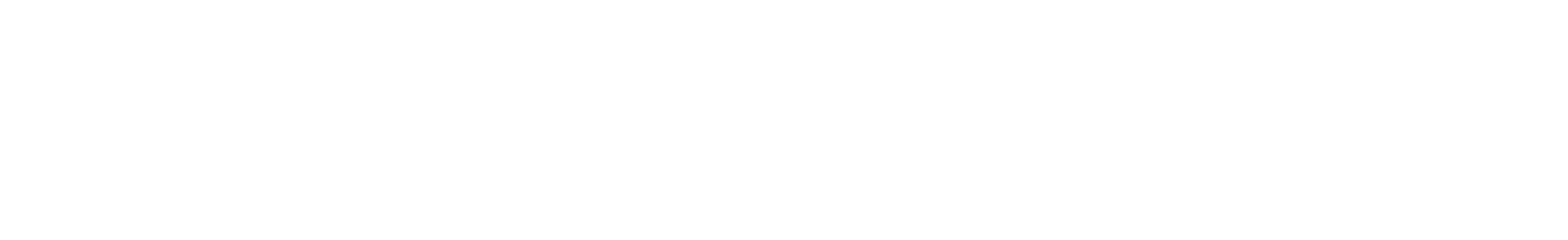職業倫理の昔と今と未来

患者への虐待がとりだされる昨今、あたりまえではあるが、精神科で勤務するスタッフは高い職業倫理をもって従事しなければならない。私が精神科病院で働くようになったのが、今から30年ほど前。ときどき昔を思い出すことがある。それは今とはかけ離れている倫理観。どうやって倫理は変化していき、何が理想なのか。
今日はタブーともいえる当時のあり得ないエピソードを二つ紹介しながら倫理観の変遷について私の思いを話していきたい。
【院内どこでも喫煙OK】
昭和から平成初期の時代は電車の中や病院の待合室でも喫煙が許された当時は今ほど喫煙者が嫌悪されることはなかった。同様に当時の精神科病院でも“喫煙のモラル”は現代人からしたら驚かれることばかり。院内に喫煙室など分煙するものはなく、ホールや病室、ナースステーションにまであらゆるところに灰皿が設置され、患者さんや看護師は好きな時に喫煙することが許されて?いた。
【看護師の方が楽しんでいた作業療法】
精神科病院おける作業療法とは精神科治療におけるリハビリテーションの一つであるということは昔から変わらない。作業療法の内容は主に退院後に必要な生活技能訓練や集団療法がある。ほかにも創作活動やストレス発散を目的にカラオケや屋外でのスポーツなども行われる。看護師はこれらのサポート業務を担当するのだが、当時を振り返ると、ソフトボールや卓球などでは患者よりはしゃいで楽しんでいたのは私だけ?
「精神科医療の歴史」というタイトルで研修会の教壇に立つことがある。これらのエピソードを話すと、ベテラン看護師にはバカウケすることは間違いなく、若い受講者は皆「ウソでしょ?」といった表情を見せる。では、昔の精神科医療現場ではヘンテコな事ばかり行なわれていたのか。看護師の職業倫理は狂ったものだったのか。おじさん看護師を代表して“それは違う”と断言しよう。
批判覚悟で言わせてもらうと、当時は“タバコは患者との良きコミュニケーションアイテム”、“作業療法は患者と一緒に楽しむこと”…。これらはマニュアルには載ってないものの、当時新人教育で先輩から習ったことで、もちろん真面目にそれを受け止めていたし、このような風潮は当時全国各地で土着的に広がっていたような気がする。
少し話を変えよう。精神科薬物療法においては今でこそ単剤療法が主流になっているが、ひと昔までは多剤併用療法が殆どであった。現在において多剤併用を“悪”、ベンゾジアゼピン製剤も“悪”と考えている方が大多数を占めるだろう。では、非定型抗精神病薬が誕生していない頃の昔の医者の職業倫理はおかしかったのだろうか。
病名においてもそうだ。統合失調症という呼称は昔、精神分裂病と言われていた。病名が変わった由来は皆さんご存じの通り。その前は早期性痴呆と呼ばれ、またそれよりもっと昔にさかのぼると“狂”や“乱”といったマイナスイメージを連想させる文字がつく表現になっていたものが多い。
話を戻しながら、私なりにまとめると、今現在正しいとされている精神科医療の倫理観は全て正しいことなのか常に疑問視する慎重さが重要だということ。数年先、数十年先の未来はもしかすると今までの常識を覆すパラダイムシフトが起きているかもしれない。これを読んだ皆さんはどのような未来予想をされるだろうか。
統括管理責任者
高田修治